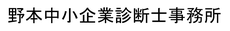久々の書籍紹介です。基本他にネタが無い時にやってきます(笑)。
これまでと紹介の順序を少し変更しました。
タイトル 仕事ができる人の当たり前
出版社 ダイヤモンド社
著者 西原 亮
価格(税別) 1,600円
中小企業経営者 ☆☆☆
中小企業診断士勉強者 ☆☆
<紹介&感想>
今回は市川市で牛乳配達店を運営しているニッシーさん((笑)の初出版本になります。直接お会いしたことはありませんが、Youtubeでお世話になっています。
https://www.youtube.com/@cooker8
新人社員が働き始めるためのアドバイスでありますが、我々ベテランにもためになることが多々入っていますので、是非参考にしてみてください。実際バラバラに入っています(笑)。第6章は具体的すぎるので省いています。
<内容>
第1章 仕事ができる人の「考え方」の当たり前
・わかったふりをしない。
・「事実」と「主観」を切り離すー事実は〇〇で、私の主観は△△です。
・価値を出すことに集中するーそこまでのプレゼンは必要か?
・不要なものをぞき落とすーどうしたらサボりつつ、求められている成果を出せるか?
ー関係者、上司を不要なものを決めることを行う
・シングルタスクに切り分けるー作業単位でシングルタスク化する
・再現性ある仕組みを作るーフィードバックをもらって反映させる
第2章 仕事ができる人の「コミュニケーション」の当たり前
・まずはl言葉を定義する
・形容詞、副詞を使わないーあいまいな言葉を排除する
・上司に答えを聞かないー上司と自分とのギャップを無くす
・5つの「ない」を守るー①分からない言葉をスルーしない、②答えを当てにいかない、
③同期で群れない、④陰口をたたく人の近くに行かない、⑤笑顔を絶やさない
・昭和的ビジネスマナーを守るー対新人:ビジネスマンの半分以上は昭和生まれ
・根拠ばかりを求めないー対新人:明確な根拠を出すのは難しい
・そのままの感情を伝えるー対ベテラン
:根拠が示しずらいことに対しては「・・・・私は悲しい気持ちになった」などと感情を素直に伝える
・自ら指摘を求めるー対新人
第3章 仕事ができる人の「チームワーク」の当たり前
・悪い知らせを最初に知らせる
・相手の期待を言語化するー相手の期待を言語化し、合意するように自ら動くーさらに、
「そもそも」にて無駄を省く
・頼ることをあきらめないープレーヤーとマネージャーの違い
・仕事を階段にして渡すー相手が何をどこまでできるかを把握し、ToDoを分解して渡す
第4章 仕事ができる人の「ToDo」の当たり前
・今週やるべきことを明確にする
・実行できる単位まで分解するー①最終のゴールを握る、②道筋をつける、③ToDoを実行する
・最終のゴールを握るー①成果物の中身は具体的に何か、②どのようなアプトプット(成果物)が良いか、
③いつまでにできていればいいか、④どのようなステップで進めればいいか(承認者への確認方法、時期等)
・ToDoをもれなく洗い出すー①ToDoに漏れがないか確認する、②ToDoを見てそのまま実行
できるか確認する、③必要に応じてさらに細かいToDoまで落とし込む
・確認は一括にまとめるーカテゴリーごとにまとめるー実行できる単位でToDoを分解し、
メンバーに任せることがマネージャーのできること
・ToDoの障害を想定する
・依存関係のToDoを優先する
・スケジュールは2種類作るーいつ何があるか、いつ何をするか
・締め切りぎりぎりで仕事をするー最も生産性高く集中する方法
・4分間だけやってみるーやる気が出ない時に対応策
第5章 仕事ができる人の「会議」の当たり前
・無駄な会議に何となくでない
・会議の終わりを明言するーこの会議は何が終わったら終わりなのかを明言する
ーより具体的な会議の目的の決定ー終了後に目的を達成したかの振り返りを行う
・ファシリテーターをするーできるファシリテーターの要件ー①会議の目的をづずれないようにする、
②参加者がフラットに議論できる場を作る、③抽象化と具体化をする、
④ネクストアクションで「誰が、何を、いつまでに」を明確にする
・発言力のある人に迎合しない
・参加者ごとの目的を伝える
・「忌憚なく」と言わないーファシリテーターが会議参加者の防波堤になる
・最初の5分は雑談するーアイスブレイクー①参加者の名前を呼び、個別に認識させる、
②オープンクエスチョンを投げる、③感謝を伝え、肯定する
・「はい」か「いいえ」で答えさせるー発言を全員に振り、同じ回数だけ意見を求めるようにバランスを
とるために、最初は応えやすい質問をする。発言回数が3回以上になったらオープンクエスチョンをする
・質問ではなく翻訳するー参加者によっては言語化能力に差があるので、わかりずらい発言を言い換える
・論点を表示し続ける
・誰が、何を、いつまでにを決める
・議事録で論理的思考を鍛えるー①会議の内容を討議テーマごとにカテゴリーでまとめる、
②各カテゴリーごとに決定した事項を記載する、③その決定された根拠となる会話を記載する
・発言にない言葉を補完するー①あいまいな言葉は一切使わない、②5W1Hの観点で補足する、
③会議の発言内容で不足があれば、自ら発言し内容を補足するように務める
第7章 仕事ができる人の「インプット」の当たり前
・本は読み切らなくていい
・本は1分以内に買う
・本は答え合わせに買うーほんの読み方ー①まず目次を見る、内容は見ない、②各目次で何か書かれているか
について自分の仮説を書く、③各目次の該当箇所を読んで答え合わせをする
・スライド3枚にまとめるー①書籍の要旨(どんなテーマ、筆者が重要視する主張ーメッセージは、
②具体的な内容(各テーマの結論とその根拠)、③学び(ギャップは何か、具体的にこの知識をどう活用
していくか)
・1時間語れるまで調べるー全ての関連事項をー①人に説明する前提で調べる、②自分の言葉で言い換えられる
ようにする、③どんな質問でもこたえられるようにする
・「~らしい」を使わないーあらゆる仕事の根本は人を動かすことー根拠を持って説明ができるように
情報をインプットする3つの観点ー①それは何?(What is it?)、②なぜそうなの?(Why so?)、
③だから何なの?(So what?)
・仕事以外でお金を稼ぐーキャリアアップ、副業、会社設立、投資
*第6章は省略しています。